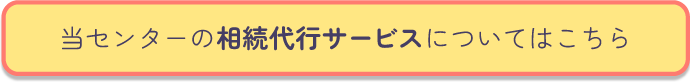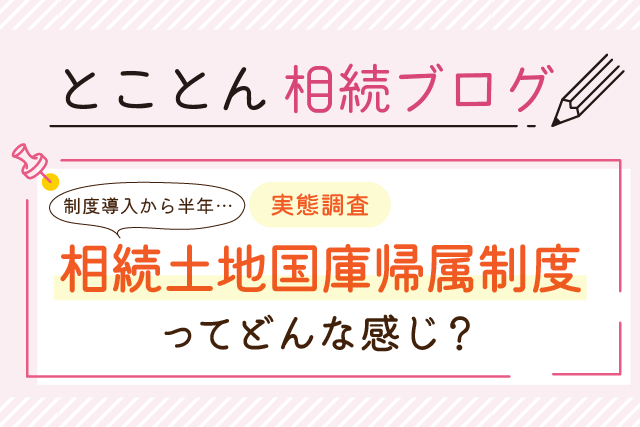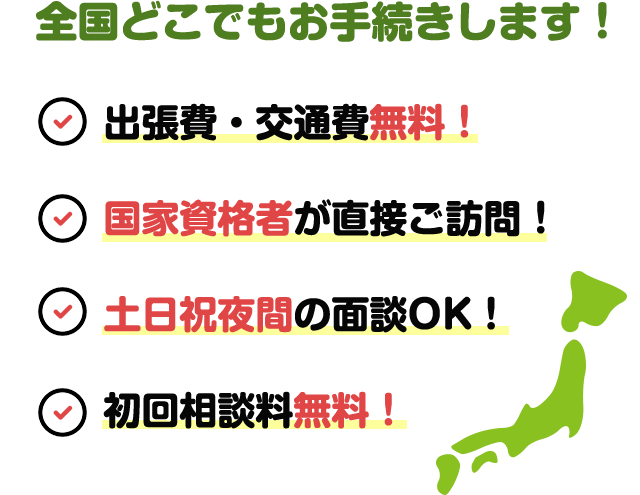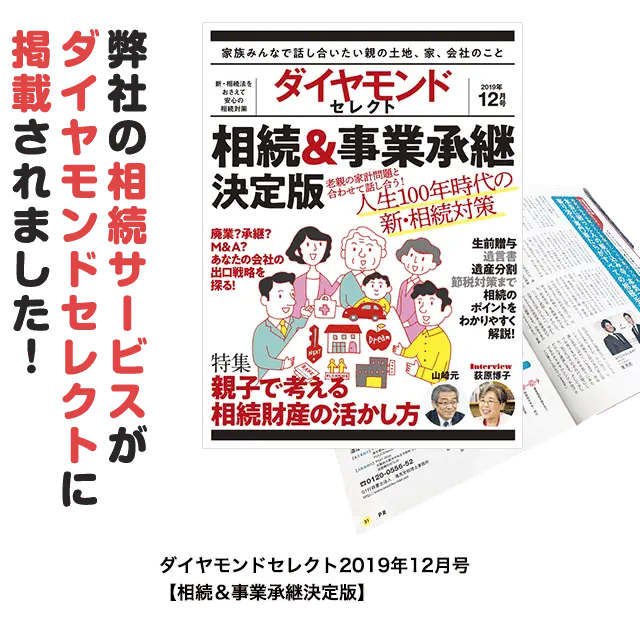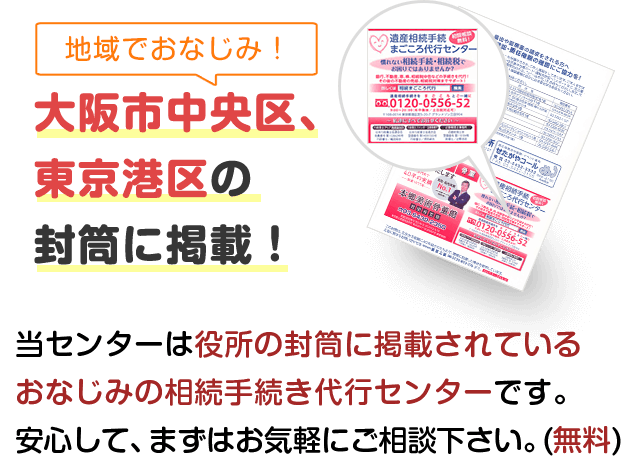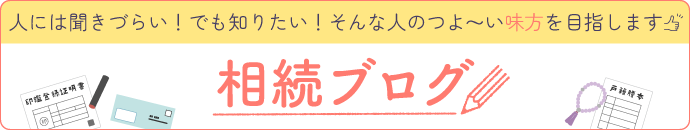
こんにちは。
遺産相続手続まごころ代行センターです。
今回は2023年4月からスタートした「相続土地国庫帰属制度」によって国庫帰属された土地の「その後」についてのお話です。
「国庫帰属した後はもう国のものなので私は知らないよ~」という気持ちはもちろんわかりますが、どのように活用されているのか、というか「要らない」「管理ができない」から国庫帰属させたものなので、そもそも活用できるのか??という疑問もあるかと思います。
ではなぜ今回はこの話題かというと、拝見したニュースがこちら!
(2025年8月21日 朝日新聞より)
この件について、皆様にお伝えします!
(上記の記事から引用しています)
そもそも「相続土地国庫帰属制度」ってなに?
文字通り「相続により取得した土地を国庫に帰属させる(国の所有、国の管理下におく)制度」ですが、詳しくは以前のブログでお伝えしていますので、そちらをご覧いただければと思います。
制度の内容についてもざっくり解説しています!
国庫帰属した後はどのように活用されてるの?
このニュースだけでは具体的な活用の仕方について読み取ることはできなかったですが、ニュースの中に
国のものとなってもその後の活用が困難な場所もあり、国によって管理される土地が増えればそのコストも高まるため、国は管理のあり方を見直す検討を始めた。周辺への悪影響が見込まれない場所などでは管理を簡素化することも検討する。
という記載がありましたので、おそらく「上手くいっていない・・・」のではないかと推察します。
もともと「要らない」土地が放置されることで荒れ果ててしまうのを防ぐために導入された制度ですので、利用も活用も難しい土地のはずなんですよね。
だってもし価値があるなら誰も国に引き取ってもらったりしませんので^^;
相続土地国庫帰属制度の利用状況
このニュースの中には実はこれも書かれていまして、どちらかと言えばこっちの方が有益な情報かもしれないということで、引用して共有させていただきます!
制度を所管する法務省によると、今年6月末までに4001件の申請があり、そのうち1776件で国への帰属が決まった。国のものとなった土地は、農用地は農林水産省、森林は林野庁、宅地やそれ以外の土地は財務省が管理する。1776件のうち、宅地は660件、農用地は553件、森林112件、その他451件だった。
ふむふむ、約4000件の申請で約1800件の帰属が決まったということは、率的にはざっくり50%弱。
まずまずの割合な気がしますね。
そもそもの申請までのハードルが高いこともあり、申請前に断念している土地が山のようにありそうですが、要件を満たして申請までたどり着いた土地については約半数が引き取られているみたいですね。
そして地目は宅地、農用地(田、畑など)、森林(山林)はまず理解できるとして、「その他」の451件という内訳がすごく気になります(笑)
地目は不動産登記規則第九十九条に記載されていて、
田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地
と決まっているんですよね。
ここから宅地と農用地と山林を除くと…
えっ、どれを国庫帰属させたの?
とちょっと不思議に思ってしまいます。
むしろその件数が森林よりも全然多いという事実…
謎です。笑
いずれにせよ、このままのペースで引き取っても国も管理ができず結局荒れ果ててしまう可能性も出て来そうですので、制度そのものの見直しがどこかであるかもしれないですね。
以上、本日のブログでしたー!
ではでは!