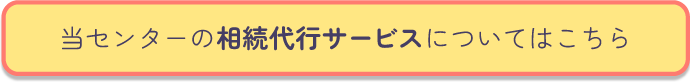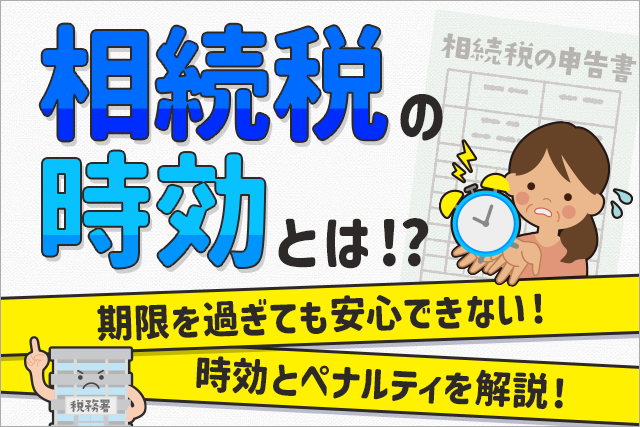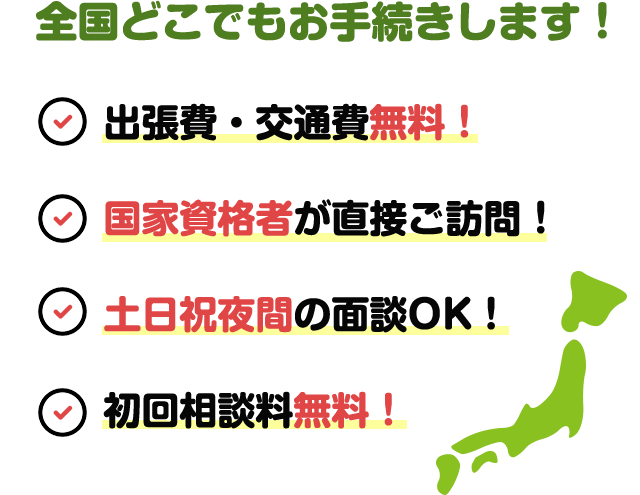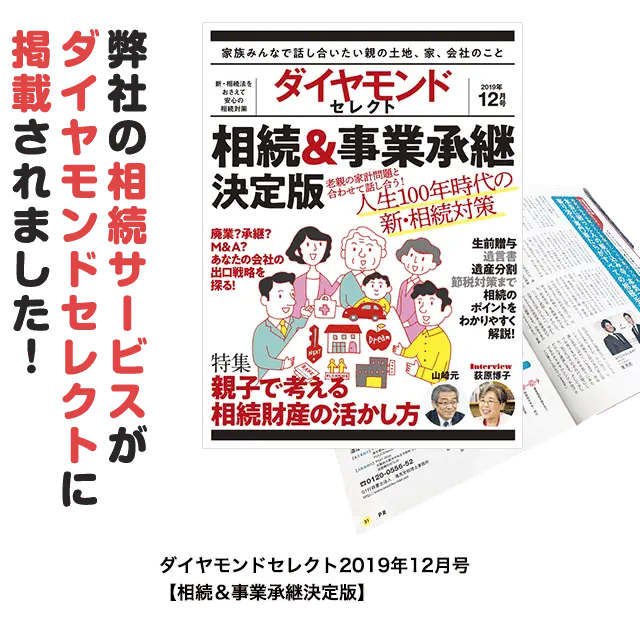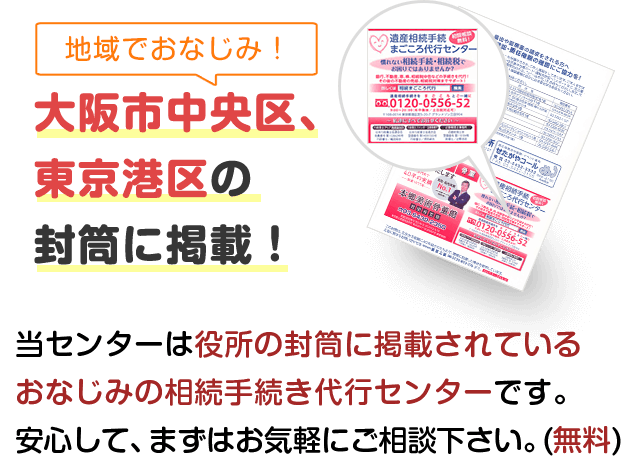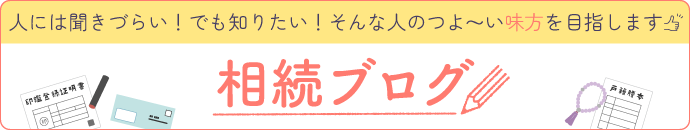
こんにちは。
遺産相続手続まごころ代行センターです。
衝撃的なタイトルで始まった今回のブログ。
AIがあらゆる分野で活用されるようになってきているのは全員が自覚していることですが、なんと「相続税調査の選定」にAIが本格活用されるとのこと。
つまり、追徴の確率が高い申告を狙い打ち・・・?
というのが、今回のテーマです。
拝見したニュースはこちら!
(2025年7月3日 Yahooニュースより)
今回はこの件について、皆様にお伝えします!
(上記の記事から引用しています)
2023年以降のすべての相続税申告書がAIによるスクリーニングの対象に
衝撃です。
まず、AIはデータを食べる(蓄える)ことで精度を限りなく高めていきますが、その対象が2023年以降の申告ということ。
2年半の膨大な申告書データを知識に変えたAIが、2025年7月1以降の相続税申告書をすべてスクリーニングします。
(スクリーニングとは、大量の対象の中から、特定の条件に基づいて、目的のものを効率的に選び出すことです)
ちなみに2024年の相続税の申告件数は約16万件。
単純計算で2.5倍すると、約40万件の申告書データを完全に把握した知能がスクリーニングをすることになります。
それによって何が起こるかというと、
- 「申告ミスや申告漏れが起こりやすいパターン」がAIの中で確立され、
- 新たに提出した相続税申告書がどれだけそのパターンに類似しているかが採点(スコア化)され、
- 採点が高ければ高いほど「調査の必要性が高い」と判断され、
実際に調査の対象となるということです!
AIが導入されるに至った背景
まず思いつくのは昨今の人材不足。
税務職員にもその波は寄せられており、国税庁の職員数は10年間で約6%も減少しているとのこと。
それとは反比例するように、基礎控除の減額や地価の高騰などにより相続税の申告件数は増える傾向にあります。
つまり、人は減っているのに作業は増えている状況ですね。
また、相続税の申告はスポット的な要素が強いので、タイミングを逃してしまうと税務調査が必要な事案であってもそれをしないまま終わってしまうというケースも起こり得ます。
相続税の申告には実は時効があるんです!詳しくはこちらの記事で
そういった「必要なのに実施できない」機会損失を減らすためにも、必要かどうかの判断のところでAIが導入されるのは当然の流れなのかもしれませんね。
ちなみに、実は2018年からAIの実証実験は開始されており、2021年から法人税・消費税の分野で本格的に稼働しています・・・!
これからの申告において注意すべきこと
不安にさせるような書き方をしましたが、AIが導入されたからと言って、正しい申告をしていれば全く気にする必要はありません。
指摘されることもないですので。
ただ、「正しい」と思って申告したけど実は正しくなかったというのが一番怖いところですよね。
- 財産の評価の方法は税理士によって見解がわかれることもあります。
- 特例の適用についても判断基準が異なることもあります。
- 「財産と思わなかった」ものが実は財産ということもあります。
- 暗号資産など新しい財産が海外の口座で管理されていることもあり、財産の内訳が本当に複雑化しています。
少しでも税務調査のリスクを回避するために、相続税の申告は必ず相続税に詳しい(特に最近の様々な財産にも明るい)税理士へ相談しましょう!