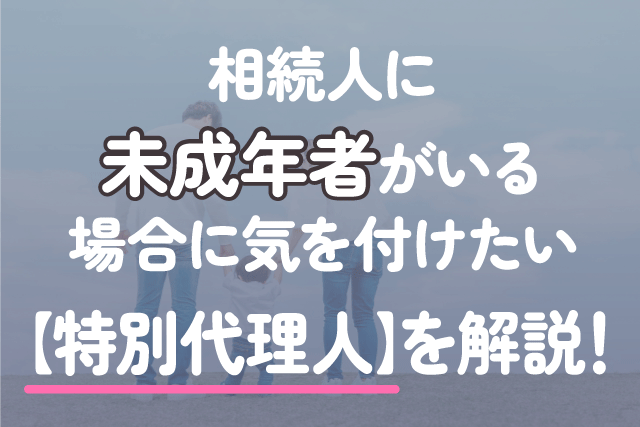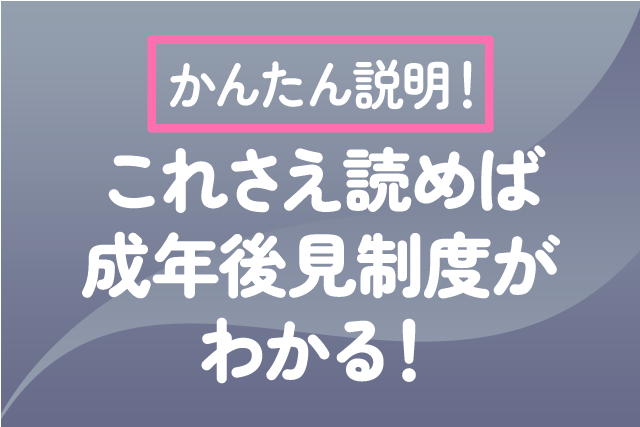- 相続において特別代理人が必要になるケースとは
→相続人に未成年者がいる場合
→相続人に成年被後見人がいる場合 - 特別代理人の選任方法
「特別代理人」とは、簡単に言うと「特別なときに必要になる代理人」のことです。
この「特別なとき」とは主に2つあり、
- 相続人に未成年者がいる場合
- 相続人に成年被後見人がいる場合
がそれにあたります。
この記事では「特別代理人」について、必要になる2つのケースとその選任方法について、解説していきます。
1.特別代理人とは
特別代理人は、代理をしてもらう人(当人)とその代理人(代理で手続きをする人)の間で、「利益が相反する行為」がある場合、選任することが民法で決められています。
「利益が相反する」ときとは、例えば「代理をしてもらう当人」と「代理人」がともに相続人であるときが挙げられます。
ともに相続人であれば、「代理人」が「代理してもらう当人」の権利も行使できてしまうため、そのような事態を防ぐために、「特別代理人」を選任することになっています。
2.特別代理人が必要になる2つのケース
相続において特別代理人が必要になるケースは、主に下記の2つです。
それぞれ解説していきます。
2-1.相続人の中に未成年者がいるケース
未成年者が相続人のとき、本来は、その親権者(両親など)が代理人になります。
ですがその親権者も相続人の場合は、未成年者のために特別代理人を選任する必要があります。
被相続人(亡くなった人):夫
相続人:妻と子(未成年)
本来であれば、未成年の子の代理人として、親権者である親が色々な法律行為をすることになりますが、親権者(妻)も子(未成年)も同じ相続人という立場になる場合は、子のために特別代理人の選任が必要になります。
また、未成年の子が複数いる場合は、それぞれの子にそれぞれ特別代理人を選任する必要があります。
2-2.相続人の中に成年被後見人がいるケース
成年被後見人が相続人のとき、本来であれば、その成年後見人が代理人となります。
ですが、その成年後見人も同じく相続人の場合は、成年被後見人のために特別代理人を選任する必要があります。
例えば、成年被後見人と成年後見人がともに相続人で、遺産分割協議をする際には、成年被後見人のために特別代理人を選任します。
3.特別代理人の選任方法
特別代理人の選任は、家庭裁判所で手続きをします。
ここでは、未成年の特別代理人の選任手続きについて、必要書類や流れなどを解説していきます。
選任手続きの流れ
①遺産分割協議書(案)を作る
②特別代理人になってもらう候補者を決めておく
(原則誰でもよいですが、最終的に家庭裁判所が決定します。)
③必要書類を集めて、家庭裁判所に申し立てる
④家庭裁判所により、特別代理人が選任される
そして、特別代理人を含む全ての相続人と遺産分割協議等の相続手続きをします。
申立先
未成年者の住所地の家庭裁判所に申立てをします。
選任手続きに必要な書類
- 申立書
- 未成年者の戸籍謄本
- 親権者の戸籍謄本
- 特別代理人候補者の住民票
- 遺産分割協議書(案)
- 収入印紙800円(未成年者1人につき)
- 切手
(申立先の家庭裁判所によって違うため、管轄の家庭裁判所に事前に問い合わせましょう。)
4.よくある質問4選
ここでは、特別代理人の選任に関してよくある質問を4つ解説していきます。
Q1:どのような人が、特別代理人の候補者になれますか?
A:特別代理人の候補者に特別な資格は不要で、未成年者の祖父母が就任するときもあります。
ただし家庭裁判所は
「未成年者(被後見人)との関係や利害関係の有無などを考慮して、適格性が判断されます。」
また、弁護士や司法書士などの専門家が特別代理人に就任することも可能ですが、その際は報酬が発生することがほとんどです。
Q2:未成年者や成年被相続人は絶対相続しないといけませんか?
A:そもそも特別代理人は、未成年者の法定相続分を確保することが前提で遺産分割協議をしますが、その結果、法定相続分を下回る協議になったとしても、家庭裁判所が相当な理由があると認めれば、法定相続分を下回った相続も可能となります。
Q3.法定相続分で相続するつもりですが、それでも特別代理人が必要ですか?
A:法定相続分で相続する場合でも、未成年者や成年被後見人のために特別代理人を選任する必要があります。
(民法で決められています。)
Q4.成年後見人に後見監督人が選任されているときでも、特別代理人は必要ですか?
A:後見監督人が選任されているときは、後見監督人が成年被後見人に代わって遺産分割協議に参加します。
(※後見監督人とは、後見人を監督するために家庭裁判所で選任された人のことです。)
5.まとめ
相続人の中に未成年者や成年被後見人がいて、本来その代理を務めるはずの人も相続人の場合は、家庭裁判所で特別代理人の選任が必要になります。
特別代理人の選任手続き自体はシンプルですが、申立書や遺産分割協議書を作成するには、専門知識が必要です。
司法書士や弁護士等であれば、手続きの代理や特別代理人の就任までしてもらうことができます。
お困りの際は、お気軽にご相談ください。