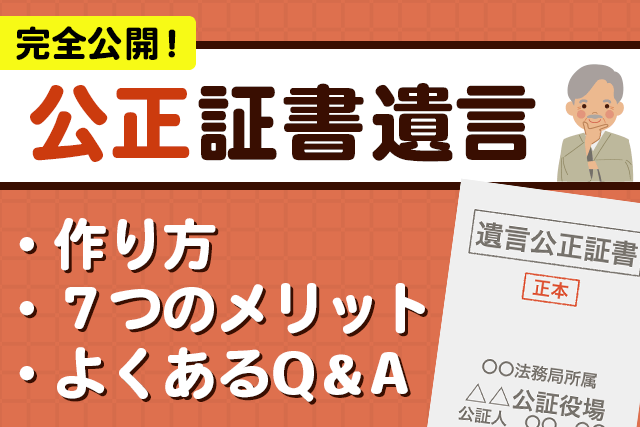- 公正証書遺言であっても無効になる場合がある
①遺言者に遺言能力がない
②遺言者が公証人に口授していない
③証人が不適格者である
④遺言書に本人の意思とは違う表記がある(錯誤無効)
⑤遺言書の内容が常識や道理に反している
- 遺言書が無効になった場合、記載の財産については遺産分割協議をする
公正証書遺言とは、公証役場で公証人と作成するため、自筆証書遺言にくらべ確実性の高い遺言と思われますが、状況によっては無効となる場合があります。
※無効となるようなケースは、他の相続人から「この遺言書は無効だ」と主張されたときに、最終的に裁判所での判断となります。
そのため、一概に「こういう状況で無効」ということはなく、状況によって判断されます。
ですが、おおよそ考えられる「無効となるケース」は5つあります。
この記事では、遺言書が無効と判断される場合のある5つのケースと、無効になった場合の相続について解説します。
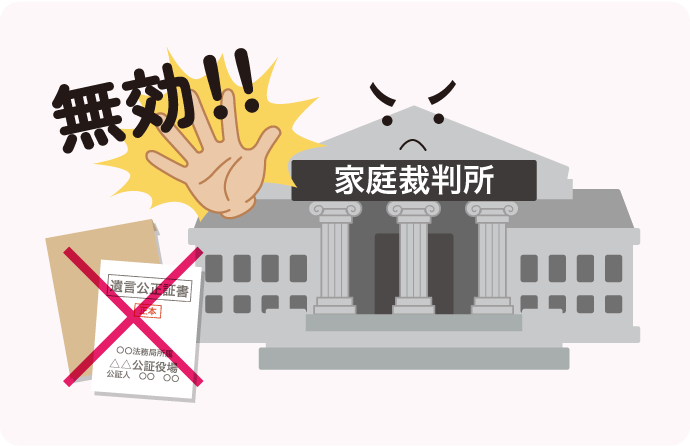
1.遺言書が無効と判断される場合がある5つのケース
裁判所に「この遺言書は無効である」と判断されるケースは5つあります。
これらについて、順番に解説していきます。
1-1.遺言者に遺言能力がないケース
「遺言者」とは、文字通り「遺言をする人」のことです。
そして「遺言能力」とは、文字通り遺言者が「遺言書を書くに足りる能力」のことです。
民法上では、「15歳に達した者は、遺言をすることができる」というように、ひとつの目安として年齢を定めています。
遺言能力がないというのは、自分の状況に正しい理解ができない状態にあることなどをいい、具体的に医師から痴呆、精神障害の診断を受けている場合などが多いようです。
ですが実際、遺言者の遺言能力の有無については、遺言時の状況を精査して裁判所が判断することになります。
そのうえで裁判所により「遺言能力がない」と判断された場合は、その遺言が自筆であれ公正証書遺言であれ、無効となる場合があります。
1‐2.遺言者が公証人に口授していないケース
口授とは「くじゅ」と読み、口頭で述べることをいいます。
民法第969条第2項
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
ちなみに、生まれつきや病気等でしゃべれず口授できない人は、代わりに筆談によって作成することが認められています。
そうではなく、公正証書遺言の作成時に口授を欠いたと判断された場合は、その遺言書は無効となる場合があります。
1-3.証人が不適格者であるケース
公正証書遺言を作成するには、証人2人の立会いが必須となります。
そして、証人は誰でもいいわけではなく、要件が設けられています。
(詳細は、こちらのページの1-3.証人を2名決めるをご覧ください。)
その条件を満たしてない人を「不適格者」といいます。
裁判所によって証人が不適格者であったと認められた場合は、その遺言書は無効となる場合があります。
1-4.遺言書に本人の意思とは違う表記があるケース(錯誤無効)
自分の意思とは違う内容を書いてしまうことを「錯誤無効」といいます。
例えば、「法的拘束力があると思い遺言の付言事項(法的拘束力はなく、メッセージ的な項目)に遺言の内容を記載してしまった」などの場合です。
こうした事実が裁判所によって錯誤だと認められた場合、その遺言が自筆であれ公正証書遺言であれ、無効となる場合があります。
1-5.遺言書の内容が常識や道理に反しているケース
難しい言葉では「公序良俗に反している」といいます。
民法第90条
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
例えば、判断能力が低下していた経営者に、「顧問弁護士に全て遺贈させる」遺言を作成させた場合などです。
そのような事実が裁判所によって認められた場合、その遺言が自筆であれ公正証書遺言であれ、無効となる場合があります。
2.遺言書が無効になったら遺産分割協議をする
1章で紹介したケースのように、遺言書が無効と判断された場合は、遺言書に記載された財産については、相続人間での遺産分割協議をすることになります。
無効となる部分が遺言書全体であっても、一部分であっても同様です。
遺言書がなかったものとして、相続手続きをしましょう。
3.まとめ
公正証書遺言であっても、状況によって無効と判断されることがあります。
そうならないためにも、自筆証書遺言であれ公正証書遺言であれ、遺言書は自分の意思できちんと作成するようにしましょう。
また公正証書遺言は、弁護士や行政書士といった専門家のサポートを受けることも可能です。
- どういう遺言にしたいのか
- 作成当日までに何が必要か
などのサポートを受けることによって、より安心な遺言書にするのもひとつの方法です。
当センターにも多数のサポート実績がありますので、お悩みの際はぜひご相談ください。