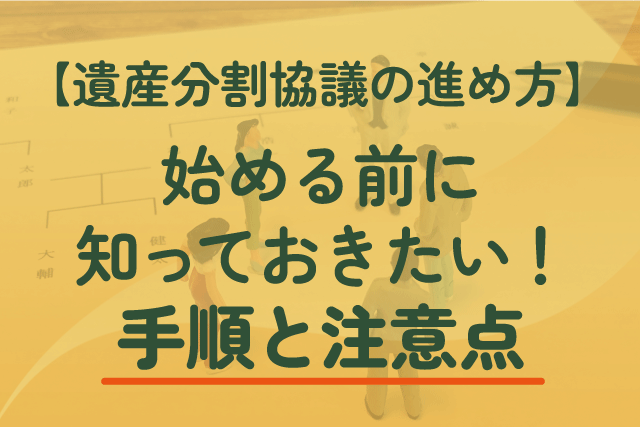- 相続人全員の合意があれば、遺言書があっても遺産分割協議はできる
- 必ず遺産分割協議の前に、遺言書の有無はしっかり確認すること
本来であれば、遺産分割協議より遺言書の内容が優先されます。
そのため、もし遺産分割協議後に遺言書が見つかったとしても、遺言書の内容が優先されます。
しかし遺言書があっても、相続人全員が「それでも遺産分割協議をしよう」と納得している場合であれば、遺産分割協議をすることは可能です。
それは遺された遺言書が、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも同じです。
この記事では、遺言書がある場合の遺産分割協議について解説します。
1.遺言書があっても「相続人全員の合意」で遺産分割協議は可能
遺言書があっても、遺産分割協議をすることは可能です。
ただし、「相続人全員が納得している」ことが必要です。
その際、相続人全員が同意していることを示すために、必ず遺産分割協議書を作成しましょう。

遺産分割協議後に遺言書が見つかった場合も、同様です。
相続人全員が納得していれば、遺言書より遺産分割協議の内容で、相続ができます。
また、「遺言書の内容は関係なくなった」からと言って、遺言書を破棄してはいけません。
破棄した場合、欠格(相続人でなくなること)になる可能性もあるため、遺言書は大切に扱いましょう。
2.もし、遺言書に相続人以外の人が関係していたら…?
もし遺言書に、相続人以外の人に財産を渡す内容があった場合はどうなるでしょうか?
この場合、相続人だけで「遺産分割協議をしよう」と決めることはできません。
(※遺言書の内容によります)
必ず、その相続人以外の人の意思(財産を受け取るのかどうか)を確認するようにしましょう。
3.まとめ
遺言書があっても、相続人全員の合意があれば遺産分割協議をすることは可能です。
(遺言書が後から見つかった場合も同様です)
ただし、遺言書が後から見つかると、面倒なことが多いです。
- 「やっぱり遺言書の内容で相続しよう!」となったり
- 「遺言書の内容を考慮して、遺産分割協議をやり直そう!」となったり
- 相続人以外の人が財産を受け取ることになっていたり
する可能性もあります。
場合によっては相続手続きが二度手間になることもあるため、遺産分割協議や相続手続きを進める前に、必ず遺言書があるかしっかりと確認しましょう。
遺産分割協議が終わった後に遺言書が見つかった、などでお困りの際は、お気軽に当センターまでお問い合わせください。