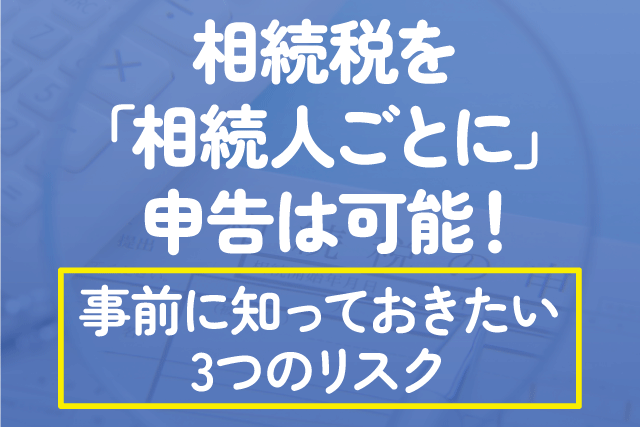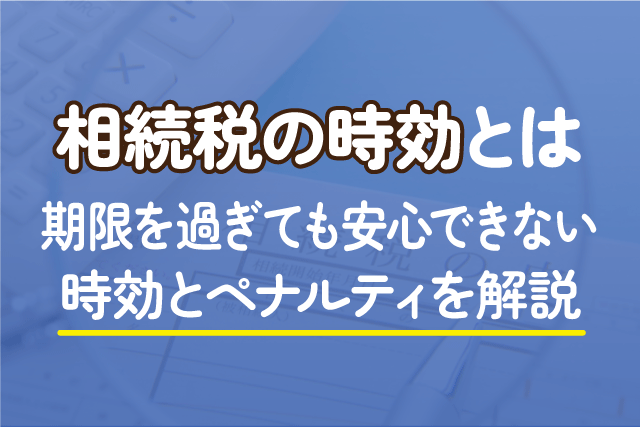- 相続税の申告期限(10か月)と起算日の考え方
- 申告期限を過ぎた場合のペナルティと、期限を過ぎると生じるデメリット
- 「とはいえ期限に間に合いそうにない…!」といった場合にできること
相続税の申告期限は10か月と決まっています。
それまでに、相続人と相続財産を確定させ、申告書を作成し、相続税を納付する必要があります。
もし期限内に申告しなかった場合はペナルティや、仮に遅れて申告したとしてもデメリットがあります。
とはいえ、「そうはいっても間に合わない!」という状況も起こり得ます。
この記事では、相続税申告の期限の考え方や、期限を過ぎてしまった場合のペナルティやデメリットについてご説明します。
目次【本ページの内容】
1.〈申告期限は10か月〉起算日と、期限を延長したい場合について
「相続税の申告期限は10か月」というのは、すでにご存じの方が多いかもしれません。
ですが、大切なのは「いつから数えて10か月なのか?」という起算日です。
ここではまず、申告期限の起算日について、また、特別に認められている期限の延長について説明します。
1-1.起算日の考え方|いつから10か月なのか?
国税庁HPの言葉を借りると、
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。
ポイントとなるのは、「被相続人が死亡したことを知った日」です。
ほとんどの場合、死亡した当日にその事実を知ることになると思いますので、「死亡したこと知った日」=「死亡日」となります。
ただし、災害等に遭った場合や孤独死をした場合は、必ずしも亡くなった日にその事実を知ることができるとは限りません。
その場合は「死亡したこと知った日」=「死亡日」ではなくなりますので、考え方が少し変わります。
ただし、稀なケースとなりますので、例外における起算日の考え方については、後述する例外に関する章をご覧ください。
ちなみにですが、相続税の納付の期限も、申告期限と同じ日になります。
「申告」して一安心ではなく、「納付」まで終わって相続税の申告は完了しますので、注意が必要になります。
注意点でいうと、もうひとつ気を付けたいことがあります。
それは、相続人が複数いる場合です。
もし別々に申告をしていたり、もしくは一緒に申告はしているものの別々に納付したりする場合、自分は納付していても、他の相続人が納付をしなかったら、連帯責任で連帯納付義務というものが発生してしまいます。
1-2.起算日における4つの例外
起算日に関する例外を、4つご紹介します。
(1)失踪の宣告を受けて死亡したとみなされた者の相続人または受遺者
被相続人が失踪宣告を受けて死亡したとみなされた場合は、宣告があった日を亡くなった日とします。そして、その翌日から10か月が申告期限になります。
(2)相続について既に生まれたものとみなされる胎児
夫が亡くなった時に妻のお腹の中に赤ちゃんがいた場合は、お腹の赤ちゃんも相続人になります。
この赤ちゃんの相続税の申告期限は、法定代理人(※)が赤ちゃんの“出生を知った日”=生まれた日の翌日から10か月が相続税の申告期限となります。
(3)相続開始の事実を知ることのできる弁識能力のない幼児
例えば夫が亡くなった時に、妻と子どもがいればこの2人は相続人になります。
子どもが18歳以上であれば、原則通り亡くなった日から10か月以内が申告期限になるのですが、18歳未満の相続人がいる場合は、法定代理人(※)が相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月が申告期限となります。
上述の(2)と(3)に関係する話ですが、赤ちゃんも含め、18歳未満の未成年が相続人にいる場合は、法定代理人をたてて相続税の申告をする必要があります。
そのため、通常とは異なり「その法定代理人が、相続の開始があったことを知った日(相続開始の時に法定代理人がいないときは、後見人の選任された日)」の翌日から10か月が、申告期限とされています。
(4)遺贈によって財産を取得した者
遺贈とは、遺言で相続人以外の人に財産を渡すことを言います。
相続人以外ですので、遺贈を受ける人は、亡くなった日にその人の死亡を必ずしも知れるとは限りません。(遠い親戚や、そもそも親戚以外の人かもしれませんしね。)
そのため、このケースでも例外が適用されて、“自分のために財産の遺贈があったことを知った日”が起算日になり、その日の翌日から10か月が相続税の申告期限になります。
1-3.〈特別な場合において〉申告期限を延長する方法
相続税の申告期限は原則として延長することはできません。
しかし災害があった場合や遺言書が見つかった場合は、申請をすることで相続税の申告期限を2か月延長することができます。
ちなみに、コロナにかかった場合も災害があった場合の期限延長として認められ、その際には「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することになります。
【コラム】期限日が土日祝の場合はどうなる?
期限日が土曜日、日曜日、祝日などの場合は、その翌日が申告期限になります。
例えば2022年7月3日にお母様が亡くなられたとします。
相続税の申告期限は2023年5月3日になるのですが、ゴールデンウィークで祝日です。
この場合は、翌週の月曜日2023年5月8日が申告期限になります。
2023年5月3日(水)祝日(憲法記念日)※本来の申告期限
5月4日(木)祝日(みどりの日)
5月5日(金)祝日(こどもの日)
5月6日(土)
5月7日(日)
5月8日(月)申告期限、納付期限!
2.申告期限を過ぎた場合|ペナルティとデメリットについて
前章でお伝えした申告期限を過ぎると、どうなるのでしょうか?
ここでは、期限を過ぎた場合のペナルティと、期限を過ぎてしまうデメリットについてご説明します。
2-1.申告期限を過ぎたときのペナルティ
申告期限内に申告をしなかった場合は、延滞税や加算税などがあります。
詳しくはこちらをご参照ください。
2-2.申告期限を過ぎてしまうデメリット
期限を過ぎてしまうと、ペナルティはもちろんですが、デメリットも存在します。
相続税は期限内に申告することで受けられる特典があるのですが、それらの特典を受けられなくなってしまうのです。
特に、小規模宅地等の特例と配偶者控除を受けることができなくなり、相続税額が大きく跳ね上がってしまいます。
小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例とは、ざっくり言うと土地の評価額を大きく下げることができる特例です。
減額できる金額はなんと80%!
例えば1億円の土地であれば、80%減の2,000万円で評価することができ、【評価額が下がる=相続税額も下がる】ということになります。
評価額を大幅に下げられる特例ですが、誰でも使うことができるわけではありません。
細かい要件等は割愛しますが、一番大事なポイントは、期限内に遺産分割が完了し、申告も期限内に完了させる必要があるということです!
どうしても期限内に完了しない場合は、未分割の申告書と一緒に、「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を提出するようにしましょう。
このときには小規模宅地等の特例を適用しての相続税の計算はできないのですが、その後、遺産分割協議が完了したときに、更正の請求(税額の還付を受けるための手続き)をして、税額の還付を受けることができます。
(※未分割については、3章で説明しています。)
配偶者控除とは
先の小規模宅地等の特例と同様に、相続税額を大幅に減らすことができるのが配偶者控除です。
これを使えば、配偶者の取得する財産は1億6,000万円まで相続税がかかりません。
かなり大きなインパクトがありますよね。
配偶者控除の適用を受ける際は、小規模宅地等の特例と同様に申告期限内に遺産分割協議を完了させ、申告を行う必要があります。
もし申告期限までに遺産分割協議書が完了しない場合は、小規模宅地等の特例のところでご説明したように、未分割の申告書と一緒に、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出する必要があります。
その後、更正の請求をして配偶者控除を適用して計算した税額との差額を還付してもらうという手続きを行うという流れになります。
3.申告期限が過ぎそうなときにできること
「相続税の申告期限を延長できるものに該当しないけれども、申告期限までに遺産分割がまとまらず、申告期限を過ぎそう…」
そんな時は、未分割で一旦提出することをオススメします。
未分割というのは言葉の通り、分割の話し合いがまとまっていない状態を言います。
具体的にどのように申告書を作るかというと、相続人がそれぞれ法定相続分で取得したものとして相続税の計算を行うことになります。
未分割で申告書を提出するときの注意点としては、デメリットのところで書いたように、相続税の減額に関する特例を受けたい場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出する必要があります。
これを忘れてしまうと特例を受けることができなくなりますので、注意しましょう。
※参照:国税庁HP(No.4208 相続財産が分割されていないときの申告)
4.まとめ
繰り返しになりますが、相続税の申告期限は10か月です!
起算日の考え方や、「期限に間に合わない…」といった対策について、ぜひこの記事を参考にしていただければと思います。
申告期限を過ぎるとペナルティやデメリットがありますので、早め早めの行動が大事になります。
とはいえ、身近な家族が亡くなって心の整理ができないまま、慣れない手続きをするのは大変ですよね。
そんなときはぜひ私たち専門家を頼ってください!
遺産相続手続まごころ代行センターでは、遺産の相続手続きから相続税申告まで、ワンストップでサポートさせていただきます。
些細なことでも大丈夫ですので、相続でお困りの際はご相談ください。
まごころ込めてお手伝いいたします。